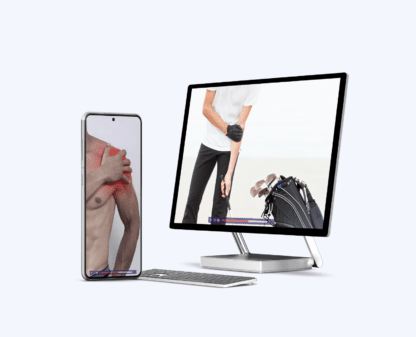橈骨遠位端骨折リハビリのための理学療法またはホームエクササイズ

はじめに
橈骨遠位端骨折は高齢者の転倒に伴う一般的な合併症である。 発症率は今後数年で上昇すると予測されている。 現在のところ、エビデンスに基づいたリハビリテーション介入はまだ確立されていないが、橈骨遠位端骨折の発生率は今後増加すると予想されているため、これは驚くべきことである。 閉鎖整復術を選択した場合、通常はギプス固定を行い、その後理学療法を紹介するか、自力で運動を行う。 橈骨遠位端骨折のリハビリテーションに関するこれまでの研究では、さまざまな結果が得られており、長期的な比較研究が必要である。 2020年のReidらは、運動とアドバイスにモビライゼーション・ウィズ・ムーブメントを加えることで、上弯の可動性の回復が早まることを発見した。 これは2000年に発表されたWakefieldと Wattによる古い研究の結果と矛盾するもので、理学療法治療の必要性を疑問視するものであった。 そこで、今回のRCTでは、ギプス固定後の橈骨遠位端骨折のリハビリテーションについて、エクササイズとモビライゼーションテクニックからなる指導付き理学療法が、セルフエクササイズからなる在宅エクササイズプログラムより優れているかどうかを比較することで、最善の方法を明らかにしようとした。
方法
この研究の目的は、60 歳以上の患者の機能改善と痛みの緩和のために、監督下での理学療法が在宅運動プログラムよりも遠位橈骨骨折のリハビリテーションのより効果的な選択肢であるかどうかを判断することです。
設計と設定: この研究は、チリのサンティアゴにあるサンボルハ・アリアラン臨床病院で行われた単盲検無作為化比較試験である。 倫理的承認が得られ、試験は前向きに登録された。
参加者たち 本研究では、A3関節外多節性橈骨遠位端骨折を有する60歳以上の患者74人を対象とした。 除外基準には、橈骨遠位端骨折の整復/固定のための外科的介入、ギプス除去後の合併症(CRPSなど)、認知障害などが含まれた。
介入: 参加者はランダムに2つのグループに割り当てられました。
- 監督付き理学療法グループ: これらの参加者は、週に2回、手首と手の運動、関節可動化、運動技能訓練を含む6週間の指導付きセッションを受けた。
- ホーム・エクササイズ・プログラム・グループ: これらの人々には、6週間にわたり、痛みの軽減、受動的エクササイズ、動的筋肉エクササイズに重点を置いた自宅での運動療法が指導された。
指導付き理学療法群は、6週間にわたって構造化されたプログラムに参加し、週2回、12回のセッションに参加した。 各セッションは、手首と手の機能を改善し、痛みを軽減し、全体的な可動性を高めることを目的としたいくつかの要素で構成されている。
- 各セッションの前半は、34℃に設定されたジャグジーで15分間、手首と手の運動を行った。 温水は関節の可動性を高め、こわばりを軽減し、関節と筋肉をその後の介入に備えるのに役立った。
- ワールプール・エクササイズに続いて、患者は関節モビリゼーション法を受けた。 最初の2週間は、メイトランド・テクニック(グレードIIまたはIII)が適用された。 このテクニックは、1秒間に1回のサイクルを1分間続けるもので、関節の可動性を向上させ、痛みを和らげることを目的としていた。 残りの4週間は、持続的なグレードIのグライドモビライゼーションを含むカルテンボーン法が用いられた。 これらのモビライゼーションは、橈骨遠位端がニュートラルポジションで安定した状態で前後方向に行われ、関節の完全性を維持し、可動性を高めた。
- さらに各セッションでは、手の機能と協調性を向上させるよう調整された運動技能訓練も行われた。 これらのエクササイズは、視覚的圧力バイオフィードバックによるコントロールされた握力エクササイズ、第一骨間腔の精度に焦点を当てた逆ダーツ投げエクササイズ、肩甲骨後退エクササイズで構成されていた。 痛みや筋疲労を防ぐため、患者はこれらの運動を短時間、低強度で繰り返し、各運動を8~10回行い、各作業を5秒間維持し、作業の合間に10~30秒間休息した。
ホームエクササイズプログラムのグループは、6週間のレジメンに従い、毎日自宅でエクササイズを行った。 最初に、各患者は理学療法士とアポイントを取り、理学療法士からエクササイズの詳しい指導を受けた。 プログラムは3つの段階に分けられ、それぞれ約2週間にわたる。
- 最初の2週間は、痛みの軽減と浮腫のコントロールを優先した。 患者は、指のストレッチや広げる運動、握力の運動、前腕のストレッチ、肘の曲げ伸ばしなどの穏やかな活動に取り組んだ。 また、肩の可動性を維持するために、腕の外転・内転、外旋・内旋も行った。
- 3週目と4週目には、抵抗のない初期の能動的な動きに重点を移し、先に紹介した指と握力のエクササイズを続け、前腕、肘、腕の動きを取り入れて関節の可動性と筋力をさらに高めた。
- 最後の2週間は、筋力をつけ、手首と手の機能的な使い方を改善するために、軽い抵抗を使ったダイナミックな筋肉運動を取り入れた。 患者は以前のエクササイズを続けながら、徐々に強度を上げていった。
自宅でのエクササイズは1回1時間で、患者は毎日エクササイズを行うことが求められた。 理学療法士は週1回の電話連絡でアドヒアランスをモニターし、エクササイズの頻度と量をチェックした。
アウトカム指標: 主要アウトカムは、患者評価手関節機能評価法(Patient-Rated Wrist Evaluation:PRWE)を用いて評価した手関節と手の機能であった。 100点は最悪の機能スコアであり、0点は障害がないことを表す。 臨床的に重要な最小差(MCID)は15点である。 副次的アウトカムには、疼痛強度(VAS)、握力、手関節屈曲-伸展可動域が含まれた。
結果
指導付き理学療法群では、自宅での運動群と比較して、6週間後および1年後の手関節機能の改善が有意に大きかった。 2年後、その差は減少し、監視下理学療法にわずかな改善がみられただけであった。

副次的アウトカム:
- 痛みの強さ: どちらのグループも痛みの軽減を報告しましたが、監督下の理学療法グループでは 6 週間後と 1 年後に痛みの軽減がより顕著でした。 2年後には、その差は最小限になりました。
- ロム: 監督下の理学療法群では、6 週間後と 1 年後に手首の屈曲と伸展において大きな改善が見られました。 この効果は2年かけて減少しました。
- 握力がある: 指導付き理学療法群では、2年間の追跡調査を通して握力の有意な増加が維持された。

質問と感想
この試験は、短期的(6週間)および中期的(1年)に手首の機能を改善するために、指導付きの橈骨遠位端骨折リハビリテーションが重要であることを示している。 橈骨遠位端骨折の自然史を見ると、骨折後1年経過した時点で可動域と握力が低下していることが研究で示されている。 16%の人が1年後も痛みを訴えている。 このことを念頭に置けば、指導付き理学療法を受けた介入群で示されたように、最初の1年間で機能的転帰を改善し、痛みを減少させることの重要性が理解できるだろう。
介入群に有利であった群間差が、2年間の長期フォローアップで小さくなったのはなぜか? 主要アウトカムについて考察すると、6週時点で家庭運動プログラム群では45.9点であったのに対し、介入群では27.3点であった。 そのため、MCIDの15点を超える大きな群間差が生じた。 しかし、両群のベースライン得点については言及されなかった。 したがって、ベースライン時に群間に大きな差があり、それがこのような群間差につながったのかどうかはわからない。 ホームエクササイズ群ではベースラインから6週目まで全く改善しなかったために群間差が生じた可能性もある。 したがって、いくつかの疑問が残る。 論文にはベースラインのスコアが描かれていないため、各グループがどのスコアからスタートしたのかを明確にする必要がある。 対照群が介入群よりはるかに悪いスコアで試験を開始した可能性もあり、この不確実性は考慮されるべきである。
オタクな話をしよう
この研究は前向きに登録され、介入は CONSORT 声明に従って記述されました。 2 人の外部評価者と統計学者はグループ割り当てについて知らされていませんでしたが、介入を実施した理学療法士と参加者には知らされていませんでした。 同じグループのすべての患者が同じ治療を受けられるように、介入は標準化されました。
この研究は、遠位橈骨骨折を患う高齢者の早期リハビリテーション段階において、監督下での理学療法プロトコルの必要性を強調しています。 重要なのは、この研究結果が、関節外遠位橈骨骨折の非外科的治療を受けている高齢者に当てはまることです。 サンプルの均質性、特に外科的に治療された骨折の除外により、遠位橈骨骨折のすべての患者への一般化が制限されます。
長期にわたる追跡調査の結果、監督下での理学療法は初期には大きな効果をもたらすものの、時間の経過とともにその効果は薄れていくことが明らかになりました。 握力の持続的な改善は、監督下での介入により特定の機能的向上がより長く持続する可能性があることを示唆しています。
この研究は、高齢者の橈骨遠位端骨折のリハビリテーションにおける早期の指導付き理学療法を提唱し、臨床的意思決定のための貴重なエビデンスを提供するものである。
研究から脱落した患者はいなかったことから、参加した患者にとって介入が実行可能であったことを示している可能性がある。
持ち帰りメッセージ
ギプス固定後の保存的な橈骨遠位端骨折のリハビリテーションは、短期的にも長期的にも管理下の理学療法が有利である。 2年後、介入群間の差はなくなり、握力のみが介入群で有意に向上した。 この研究は、高齢の橈骨遠位端骨折患者において、短期・中期の機能的転帰と疼痛緩和を最適なものにするために、管理下のリハビリテーションが重要であることを強調している。 自宅での運動プログラムも有益であるが、指導者付きのセッションを受けることで、より優れた初期段階の改善が得られる。 しかし、主要アウトカムのベースラインスコアは不明であり、この限界は考慮されるべきである。
参考
肩の痛みと尺側手首の痛みに関する2つの100%無料ウェビナーを見る
アンドリュー・カフ氏による「肩痛を持つ活動的な人の運動処方のための臨床的推論を改善する」、トーマス・ミッチェル氏による「ゴルファーのケーススタディを取り上げた臨床診断と管理をナビゲートする